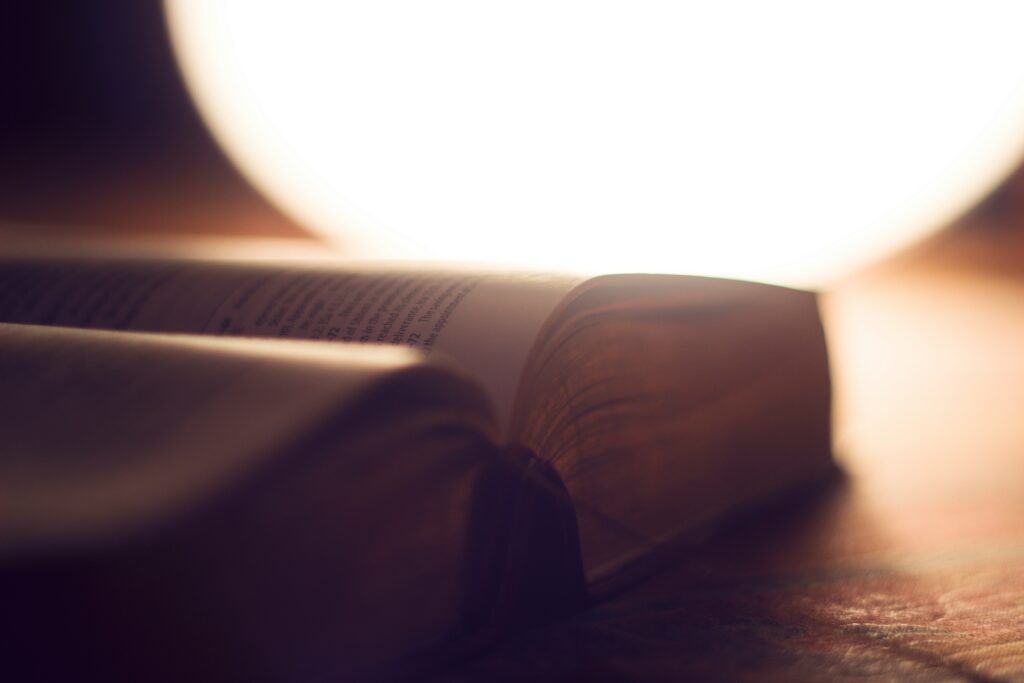
皆さんは帳簿をどのように使っておられますか?
せっかく手間をかけて作成した帳簿を決算や納税だけのために使用するのではとてももったいなく思います。今回は、帳簿をもっと活用するための視点を4つ、お話しします。
税金を正しく計算する
帳簿の金額をもとに税金の金額を計算しています。
「納税があるから帳簿をつけなければならない」といっても過言ではありません。
中には、年に一度だけ請求書や領収書をまとめて経理データを入力する方もいらっしゃいますが、それでは資料の管理が難しくなってしまうため、正しい税金を計算するという点ではあまりおすすめできません。
理想は毎日経理データを入力することですが、難しいようなら月1回の入力でも十分です。入力資料を溜めてしまうと入力するのにより大きなエネルギーが必要になるので、こまめに入力を行うと良いでしょう。
資料が不足していたり、必要のない資料が紛れ込んでいたりすると、正しい税金が計算できなくなります。納税額が本来より多くなりすぎたり、反対に少なくなってしまい、後から税務署から指摘を受けて、申告内容の修正にかかる手間や追加で納める税金(追徴課税)が生じたりと余計なコストやリスクが生じる可能性があります。
お金の流れを把握して、事業の損得を知る
帳簿を付けることで事業がうまくいっているかどうかがわかるようになります。
「利益が書いてあることぐらいわかる」と言われそうですが、実は利益にもいろいろな種類があります。
- 売上総利益
- 営業利益
- 経常利益
- 税引前当期純利益
- 当期純利益
と、損益計算書(決算書のうちの1つ。利益計算を行っている資料。)に表示されているものだけでも、5つあります。他にも、EBITDAや限界利益など色々と利益はあり、会社の課題や目的に合わせて、注目する利益も変わってきます。
上記のように、帳簿からは色々な利益がわかりますが、多すぎて何を見ればよいかわからなくなることもあるかもしれません。
どの利益を見ればよいかは、また別の機会にお話しします。
帳簿は未来を予測するための基礎データ
これからのことを予測するためには、まず何を考えるでしょうか?
今後行いたい事業や設備投資、目指すべき働き方など色々ありますが、どれもお金が不可欠になります。
では、そのお金が将来どうなるかを予測するにはどうしたら良いでしょう?
やはり、今いくら儲かっているか、赤字なのかを把握する必要があります。
予測とは、「現実」と「理想」のギャップを把握し、今後の行動によって、そのギャップをどのように埋めることができるかを考えることです。その「現実」を表してくれるものが帳簿になります。帳簿を付けることは将来のお金を予測する一歩となります。
帳簿を作成された際は、将来のお金はどうなるか、今後の行動を見直すきっかけとして活用していただければと思います。
お金は会社の血液
会社のお金は、人間でいう血液によく例えられます。血液であるお金が無くなれば、当然ながら会社は立ち行かなくなります。
では、利益が出ていればお金はなくならないのでしょうか?
利益が出ていてもお金が減ることがあります。これがいわゆる「黒字倒産」というものです。利益や売上ばかりに目を向けてしまい、貸借対照表(決算書の一部。会社のお金の状況を表す資料。)に表れる警告を見逃し続けてしまうと、黒字倒産となります。
ここが経理の難しいところで、利益とお金の増減は別物と考えなければなりません。もちろん利益が出ている方が赤字である場合と比べて、お金は増加しやすい傾向にあるのは確かですが、利益とお金の増減が完全に一致するわけではありません。利益以外のお金の変化が貸借対照表に表れてきます。例えば、融資を受けた場合や設備投資を行った場合は、そのお金の増減のほとんどが貸借対照表に表れます。
私自身、この考え方がすぐにできるようになったわけではありません。この考え方が自分の中に定着するまで2年ほどかかりました。
貸借対照表では、お金がどれだけあるかだけでなく、お金をどうやって調達したか、そのお金が何に使われたかが記載されています。特に融資を積極的に利用する場合は、貸借対照表をもとに融資計画を立てることが大切になります。
まとめ
手間をかけて作成した帳簿を上手に活用できれば、今後の事業の方向性を決める手助けになります。どう読み取ればよいかは難しいところですが、事業を行っていく中で気になるところがあれば、数字に表れていないかなどと注目し、確認してみるとよいでしょう。
まずは興味のある所から少しずつ帳簿に慣れていっていただければと思います。