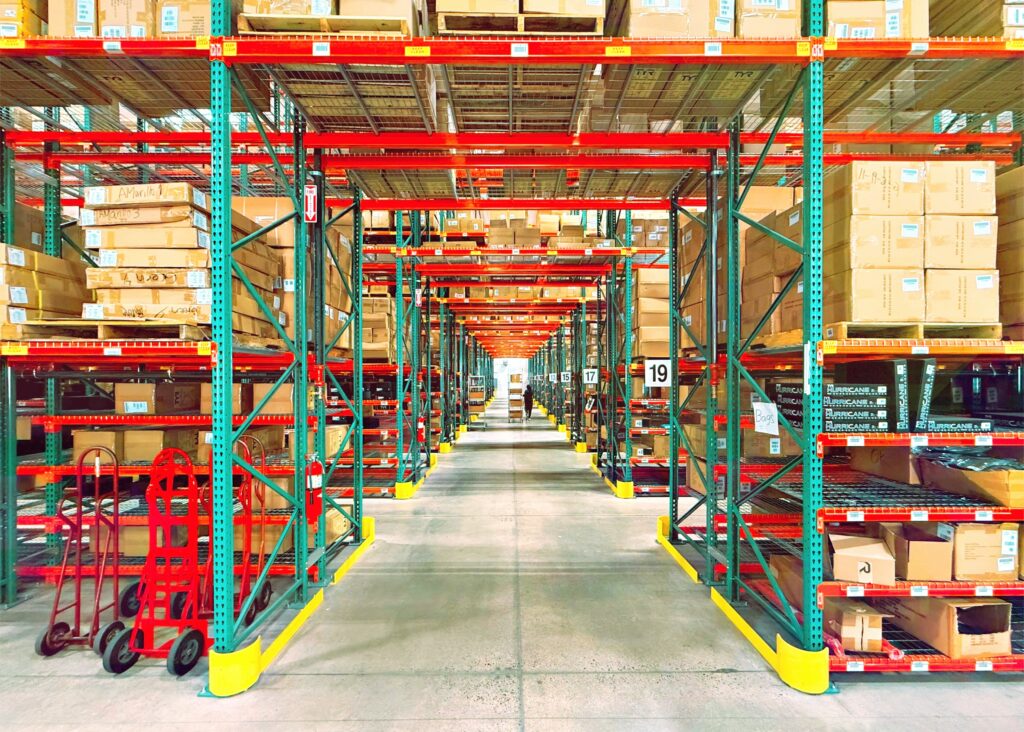
商品の棚卸はしていますか?
商品の販売がない会社では棚卸をしていない場合もありますが、多くの会社では頻度に差はあっても棚卸を行っています。
棚卸は原価と深く関係します。私も棚卸の重要性がわからず、原価が上下し、黒字に喜び、赤字に悲しみ、と毎月一喜一憂していたこともありました。ただ、毎月棚卸をしていない会社であったため、原価が安定しないことに初めは気づいていませんでした。
経理処理によっては概算になりますが、棚卸をせずとも原価を安定させることもできます。そんな原価に影響する棚卸資産についてどう管理していくか確認していきましょう。
棚卸資産とは?
まずは棚卸資産とは何かを確認していきましょう。棚卸資産とは、販売や使用のために購入したもののうち、まだ販売または使用していないもののことをいいます。
勘定科目でいうと、製品、商品、半製品、仕掛品、材料、貯蔵品などがあります。
| 製品 | 原料を自社で加工して形にしたもの |
| 商品 | 他店から購入し、加工せずに販売するもの |
| 半製品 | 製品を製造する過程で生じ、販売価値のある製品にまでなっていないもの |
| 仕掛品 | 製造途中の段階でまだ形になっておらず、販売価値もないもの |
| 材料 | 製品を製造するための原料 |
| 貯蔵品 | 消耗品などを購入して、未使用となっているもの |
棚卸資産となるかどうかはそれぞれの業種によります。たとえば、不動産会社であれば、販売する土地や建物は商品となります。小売店であれば、商品と貯蔵品がメインとなります。惣菜などを作っているスーパーの場合は、材料という棚卸資産が発生することもあるでしょう。
棚卸資産の金額はどう決める?
棚卸資産の金額計算には様々な方法があります。届出を税務署に提出することで、その計算方法を変更することができますが、届出を出していない場合は、最終仕入原価法により計算します。
最終仕入原価法とは、当期の最後に仕入れた棚卸資産の単価を使って棚卸資産の金額を計算する方法です。
この方法では商品ごとの日々の入出庫を細かく記録する必要がなく、最後に仕入れたときの単価と在庫の数量を把握することで計算でき、管理を簡単にすることができます。
ただし、最後に仕入れた単価を使用するため、それより前に仕入れた在庫が残っていても、その単価は反映されません。管理が簡単になるので、在庫をあまり保有していない会社に適した方法と言えるでしょう。
税務署に届出を提出することで、次のような計算方法に変更することができます。
- 移動平均法
- 総平均法
- 先入先出法
- 個別法
- 売価還元法
など
名称からある程度、計算の方法がイメージできるかもしれません。売価還元法以外は棚卸資産の種類・個別ごとに出入りの個数や金額を管理する必要があり、最終仕入原価法よりも厳密な管理が必要になります。在庫の管理システムを導入したり、仕組みを整えたりと、計算を行うまでに準備が必要です。
売価還元法は売価から原価を計算する方法です。多品種で多量の商品などを扱う業種の在庫管理に適しています。実際の仕入金額は使わないので、在庫の金額管理を簡略化する方法です。棚卸時に数量と値札から売価を把握して棚卸資産の金額を算定します。棚卸自体は簡略化できますが、商品群ごとでも良いので、原価を正確に計算できるようにする必要があります。
いずれも準備が必要となるので、最初は棚卸の実施のみで把握できる最終仕入原価法で金額を算定し、次第に正確な在庫管理ができるように仕組みやシステムを整えていくと良いでしょう。
棚卸資産をどうやって管理する?
最終仕入原価法を採用した場合の管理方法を確認します。
棚卸のタイミングは月末に行います。毎月棚卸を行わない会社では、決算日のみの実施となります。棚卸は「実施日」がとても重要です。実際に、棚卸のために営業を休む会社もあるほどです。原価を左右することになるので、必ず日付通りに実施するようにしましょう。
棚卸によって商品ごとの数量や仕入単価を記録した在庫一覧表を作成します。この在庫一覧表が棚卸資産の金額を確定させる根拠資料となります。日々在庫一覧表を更新している場合は、棚卸による数量が一覧表と一致しているかを確認しましょう。
在庫一覧表を作成したら、その金額を経理データに反映させます。データを入力後、改めて経理データと在庫一覧表を照らし合わせましょう。処理や計算が間違っていることもよくあります。私も棚卸資産の金額を変更したときは、必ず金額を再確認するようにしています。
毎月棚卸を行わない場合の経理処理
毎月棚卸を実施しない場合の経理処理は2通りあります。
- 期首から棚卸資産の金額を変動させない
- 概算の原価率で売上原価を設定する
それぞれの経理処理によって棚卸の影響があらわれる勘定科目が変わります。異常値が出た場合は、一度棚卸を行うと良いでしょう。
ただ、棚卸を行ったからといって原因が棚卸資産とは限りません。棚卸資産は売上原価と密接な関係があります。そのため、棚卸資産以外の要因で異常値が発生している場合でも、棚卸資産関係の金額に影響することもあります。少なくとも異常値の原因が棚卸資産にあるかどうかが棚卸の実施によって判明するでしょう。
また、次のいずれの方法であっても、決算日では必ず棚卸を行う必要があることは変わりません。棚卸の実施を忘れないように注意しましょう。
では、それぞれの処理方法を見ていきます。
期首から棚卸資産の金額を変動させない
期首から棚卸資産の金額を変えないため、棚卸資産の過不足は売上原価に反映されます。そのため、売上原価が毎月変動しますが、在庫が一定、もしくは少額の場合は、売上原価にあまり影響がないので、経理処理を簡略化できるこの方法が効率的といえます。
また、貸借対照表の確認にあまり慣れていない方にとっては、棚卸資産関係の影響が売上原価にあらわれるので、異常値を把握しやすいでしょう。
ただ、売上原価は棚卸資産だけが影響するわけではありません。特に、製造業の場合は様々な経費が影響しています。そのため、異常値が小さいうちは把握が難しく、大きな金額になってから異常値が見つかることもあります。
概算の原価率で売上原価を設定する
この方法は、毎月たとえば前期の原価率を使用して売上原価(棚卸資産の使用金額)を売上に応じた割合で固定します。そうすることで、購入した商品と販売した商品の差額を棚卸資産として残す処理を行います。
棚卸資産の金額が増減することになり、棚卸資産の金額に異常値が反映されます。棚卸資産の金額が増えているのであれば、在庫を見た時に普段より在庫が多いと感じるかもしれません。そうであれば良いのですが、在庫の量はあまり変わっていないのに、棚卸資産の金額が増えている場合は単価が上がっているかもしれません。結局のところ、棚卸を行わなければその原因はわかりませんが、売上原価に異常が出るよりも棚卸資産に異常が出たほうが、余計な経費が含まれていない分、棚卸関連の異常を見つけやすくなります。
ただ、貸借対照表を確認する必要があるため、普段から見慣れていないと正しい金額かどうかの判断が難しく、金額を見ても違和感に気づけないことも少なくありません。そうであれば、棚卸資産の金額を期首から変更しない方法の方が異常値を発見できる可能性が高いでしょう。
このように上記の方法は一長一短です。どちらが良いかは経営者が財務諸表(帳簿)をどのように読み取るかが重要になります。もちろん、毎月棚卸を行うに越したことはありません。棚卸を毎月実施できる仕組みを整える方が読み取りを強化するよりも早く異常値を発見できる可能性もあります。会社にとって何が最適かを判断して経理処理をどうするかを検討すると良いでしょう。
まとめ
経理処理は何が良いかは会社ごとに異なり、さらに会社の成長段階によっても変わります。そのときどきの状況に応じて、柔軟に判断しながら経理処理を行うことが大切です。
棚卸資産はあまり注目されませんが、検討する内容が多い勘定科目です。まずは簡単な経理処理から始め、棚卸を毎月行える仕組みを整えたり、評価方法を検討したりすることで、徐々に正確な金額を把握できるようにしていくと良いでしょう。